「自分の厄年なのに、家族ばかり不運に見舞われている気がする…」
そんな不安を感じたことはありませんか?
厄年とは、本来その年齢の人に災厄が降りかかるとされるもの。
けれど、一部では「厄年の本人ではなく、代わりに家族が厄を受けてしまう」という考え方も。
実際に、「自分は何事もなかったのに、家族が病気になった」「親や子どもに不運が続いた」という話も耳にしますよね。
こうした現象は、昔から「身代わり厄災」とも呼ばれ、厄年の対策を考える際に気にする人も少なくありません。
でも、そもそも厄年の厄は本当に「移る」のでしょうか?
また、もしそうなら、家族を守るためにはどうすればいいのでしょうか?
この記事では、
以上について詳しく解説していきます。
また、本厄と後厄ではどっちが悪いのかについても解説!
さあ、あなたの大切な家族を守るために、しっかりと対策を考えていきましょう!
目次
厄年は自分の身代わりになって家族が厄を受ける?

普通、厄年の影響を受けるのは本人だと思われがちですが、「厄を家族が代わりに受けることがある」という話もよく耳にします。
たとえば、
- 厄年の本人は元気なのに、家族が病気になった
- 厄年の年に、家族に不幸やトラブルが続いた
こんな話を聞くと、「もしかして自分の厄が家族に移っちゃった?」と心配になりますよね。
なぜ厄が家族に移ると言われているのか?本当にそんなことが起こるのか?について詳しく解説していきます!
厄年の厄が家族に移る理由
「自分は厄年なのに、なぜか家族の方が不運続き…」なんてこと、ありませんか?
実は、昔から「厄は本人だけでなく、家族に影響することがある」と考えられてきました。
この現象は「身代わり厄災」とも呼ばれ、特に親・配偶者・子どもなど、身近な人が影響を受けやすいとされています。
では、どうしてこんなことが起こるのでしょうか?
家族の絆が強いからこそ、影響を受けやすい
家族は普段から一緒にいる時間が長いですよね。
特に親子や夫婦の場合、お互いの感情や体調の変化に敏感です。
たとえば、
- 厄年の本人が仕事や人間関係でストレスを抱えると、その影響で家庭の雰囲気が悪くなる
- 厄年の人が体調を崩すと、看病する家族の負担が増え、結果的に家族の健康も損なわれる
こういった連鎖が起こることで、「厄が家族に移ったのでは?」と感じるケースがあるんですね。
厄年の人を守ろうとすることで、家族が無理をする
厄年の人がいると、家族は自然と「大丈夫かな?」と気を使うもの。
でも、それが逆に家族の負担になってしまうことも…。
- 「厄年だから無理しないで」とサポートしていたら、家族のほうが疲れ果ててしまった
- お祓いやお守りを準備するために奔走し、家族が精神的にすり減った
こんなふうに、厄年の人を支えようとするあまり、家族が厄を背負ってしまうことがあるんです。
もともと「身代わり厄除け」の文化がある
日本には、「他のものに厄を移してもらう」という考え方が昔からあります。
たとえば、
- 厄年の人が「身代わり人形」に名前や年齢を書いて神社に納める(人形に厄を移す)
- 厄年の男性が長いもの(長いお金=長寿につながる)をもらう
- 厄年の女性が赤い下着を身につける(赤は魔除けの色)
こうした風習を見ると、「厄は移るもの」という考え方が昔からあったことがわかります。
だからこそ、「厄年の本人ではなく、家族が代わりに厄を受ける」という説も、根強く信じられているんですね。
厄年の厄除けアイテムは七色のもの!自分で買うと効果なくなる?
本厄と後厄、どっちが悪い?

厄年の中でも特に注意が必要とされるのが「本厄」と「後厄」。
多くの人が「本厄さえ過ぎれば安心」と思っていますが、実は後厄こそ油断は禁物です。
後厄の方が悪いといわれるのは、本厄を乗り越えた安心感や心身の疲れによる「油断」や「隙」が、思わぬ災難を引き起こす要因になりやすいから。
家族への影響も心配…。
具体的にどう違うんでしょう?
本厄:最も注意が必要な年
本厄とは、厄年の中でも「厄災が最も強く降りかかる年」とされる年齢です。
人生の節目にあたることが多く、社会的・身体的な変化が起こりやすい時期でもあります。
本厄で注意すべきこと
本厄は「自分の身に直接災厄が降りかかる年」とされるため、厄払いを受けるならこの年がベストです。
後厄:油断した頃に訪れる試練
後厄は「本厄の影響が残る年」とされ、まだまだ注意が必要な期間です。
厄年の名残りがあり、厄除けをしていても不運が続くことがあるため、「終わった」と安心するのは禁物です。
後厄で注意すべきこと
特に、「本厄を無事に乗り切った!」と気が緩んだところにトラブルが起こることが多いので、後厄でも引き続き慎重な行動を心がけることが大切ですね。
後厄の災難が家族に及ぶ理由
後厄では本人ではなく、大切な家族が「身代わり」となって災難を受けるケースがあります。
例えば、本厄で厄払いを受けた本人は守られているのに、はじかれた厄が家族に影響するという説も根強く信じられています。
実際にあったケースとして、家族で車に乗っていて本人は無傷なのに家族だけがケガをするなど、家族がまるで身代わりになったかのような災難も報告されているんです。
実録!後厄に体験した“悪い”出来事
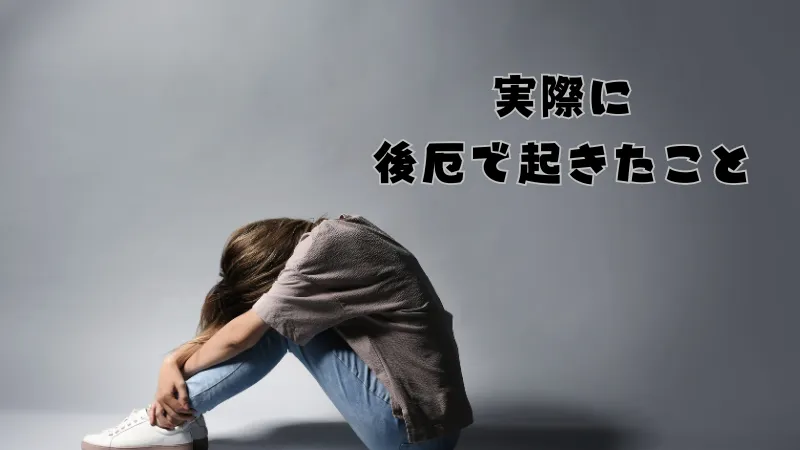
ここでは、管理人と管理人の同僚が経験した悪い出来事を紹介します!
ケース①管理人が経験した度重なる不運
2023年は、私の旦那が後厄。
9月頃から急激に、旦那の周りで悪い事が続きました。
- 9月中旬:旦那が家の庭の草刈りをしていた際、飛び石で私の車のリアガラス粉砕。
- 10月上旬:旦那の車が不調。走行中にハンドル操作が利かなくなる。
- 10月中旬:離れて暮らす長男が自転車走行中にトラックと接触事故。
- 10月中旬:メンテナンスに出して問題なかった旦那の車が再び不調に。
- 12月下旬以降:立て続けに三男が体調不良に。
思いかえせば、2023年の前半も運の悪さはあったように思います。
それでも、この短期間での出来事に、「本当にヤバいな…」と。
確かに、家族への注意喚起が出来たので、それはそれで良かったです。
ただ、本厄が終わったとしても気をつけていかなきゃな…と強く思いました。
ケース②同僚を襲う不運
私の同僚の旦那さんは、2024年が後厄。
厄年を信じていない人らしく、厄払いもしなかったそう。
ただ、同僚含め、家族には災難が続いていました。
- 車を撮った写真に、奇妙なものが写っていた
- 新車を買った1週間後、駐車場でぶつけられる
- 仕事でミス(普段では考えられない)
- 娘の突然の病気と入院
もちろん偶然かもしれません。
でも、あまりにも災難に遭いすぎて、同僚も精神的に参っていました。
お祓いに行くようにアドバイスしたら、すぐに行ってきたようで、それ以降の不運は起きなかったみたいです!
「お祓い受けた方がいいのかな?」
「とりあえず、どうしたらいいか相談したい」
そう思っているなら、こちらに相談してみるのも方法のひとつ。➡全ての悩みを有名占い師達が解決!【電話占いヴェルニ】
「でも、電話占いって高いんでしょ?」って思っているあなた。
実は今なら無料会員登録で4000円分が無料鑑定できるんです。
4000円分が無料なら、ちょっと試してみるのもいいかもしれませんね。
厄年の影響を最小限にする厄除け方法

「厄が家族に移るかも…」と心配なら、早めに厄除け対策をしておくのがベスト!
日本には、「厄を遠ざける」「厄を家族に移さない」ための厄除け方法がいくつもあります。
ここでは、効果的な方法をいくつか紹介していきますね。
神社での厄払いを受ける(最も一般的な方法)
厄除けといえば 神社での厄払い!
厄年にあたる人が神社に行ってお祓いを受けることで、厄を清め、家族への影響を防ぐことができます。
厄払いの流れ
- 厄年の人が神社に行き、「厄除け祈願」を申し込む
- 神職の方がお祓いをし、厄を払う
- お札やお守りをもらい、家に持ち帰る
おすすめポイント
厄払いを受ける時期は年始〜節分の間がベストですが、基本的には1年中いつでも可能です。
「まだ受けてない!」という方は、家族と一緒に行ってみるといいですね!
身代わり人形を使って厄を移す
「身代わり人形」は、厄年の人の代わりに厄を受けてもらうお守りのようなもの。
神社で手に入ることが多く、人形に名前と年齢を書いて、息を3回吹きかけることで、厄を移すことができます。
その後、人形を神社に納めると、神職の方が厄払いをしてくれる仕組み。
「家族に厄を移したくない!」と思う人におすすめの方法ですね。
身代わり人形が手に入る場所
- 地元の神社(厄除け祈願をしている神社が多い)
- ネット通販(最近はオンライン授与も増えている)
こんな人におすすめ!
- 「神社での厄払いには行けないけど、何か対策したい」
- 「家族に厄が移らないようにしたい」
家族全員で厄除けアイテムを持つ
厄年の人だけでなく、家族みんなで 厄除けアイテム を持つことで、家族全体の厄除け効果が期待できます。
代表的な厄除けアイテム
- 厄除けのお守り(神社やネットで購入)
- 赤い下着や小物
- 長いもの(長寿につながる)
家族全員で「これを身につけよう!」と決めると、お互いに意識し合えて安心感が増すので、ぜひ試してみてくださいね。
家の中を清める(厄を寄せつけない環境作り)
厄除けは、家の環境を整えることでもできるんです!
特におすすめなのが…
家の中を整えることで、「悪い気」を遠ざけることができるので、厄除け対策としても効果的ですよ!
厄を防ぐには「気にしすぎないこと」も大事!
厄年だからといって、「絶対に悪いことが起こる」わけではありません!
実際に何も起こらず、無事に過ごす人もたくさんいます。
ただ、「厄年が気になる…」「家族に影響が出たら怖い…」という気持ちがあるなら、厄除けをしておくことで安心感が得られるのは確かですね。
次の項目では、厄年の不安を減らし、家族全員が安心して過ごせる方法をご紹介します!
「厄をポジティブに乗り切る考え方」をチェックして、楽しい1年を過ごしましょう!
厄年をポジティブに乗り切る考え方

「厄年って悪いことばかり起こるイメージがある…」と、不安に思っていませんか?
確かに、昔から「厄年は災難が多い」と言われています。
けれど、実は厄年を前向きに捉えることで、むしろ人生のステップアップにつながるという考え方もあるんです!
ここでは、「厄年=悪いことが起こる年」ではなく、「大切な節目の年」としてポジティブに乗り切るコツを紹介していきます。
厄年は「人生の転機」と捉えよう
厄年にあたる年齢を見てみると、社会的な役割や環境が大きく変化するタイミングであることがわかります。
- 25歳(男性)・19歳(女性)→社会に出る、結婚、独立など
- 42歳(男性)・33歳(女性)→仕事の責任が増す、家庭環境が変わる
- 61歳(男性)→定年、第二の人生のスタート
つまり、厄年は人生の「大きな転機」!
「変化があるからこそ、新しいチャンスが生まれる」と考えれば、厄年も前向きに過ごせそうですよね。
厄年は「自分を見つめ直すチャンス」
厄年は、普段なかなか気にしない「自分の健康や生き方」を見直すタイミングにもなります。
厄年だからこそ、「自分を大切にする」ことを意識してみるのもいいですね!
「厄落とし」をして気持ちをスッキリさせる
「厄落とし」とは、意図的に悪いものを手放し、運気を上げる行動のこと。
「厄を落とす=新しい自分になるチャンス!」と考えると、ポジティブな気持ちになれますよ。
まとめ:厄年を家族みんなで前向きに乗り越えよう!

ここまで、 「厄年の厄が家族に移る」という考え方と、それを防ぐための対策 について詳しく解説してきました。
厄年は、単なる迷信ではなく人生の節目を意識する大切な機会です。
だからこそ、「不安を抱えたまま過ごす」のではなく、家族みんなで前向きに乗り越えることが大切!
「厄年だから不安…」と思っていた方も、正しい知識と対策を知ることで、安心して過ごせるはず!
ぜひ、家族みんなで支え合いながら、素敵な1年を過ごしてくださいね!

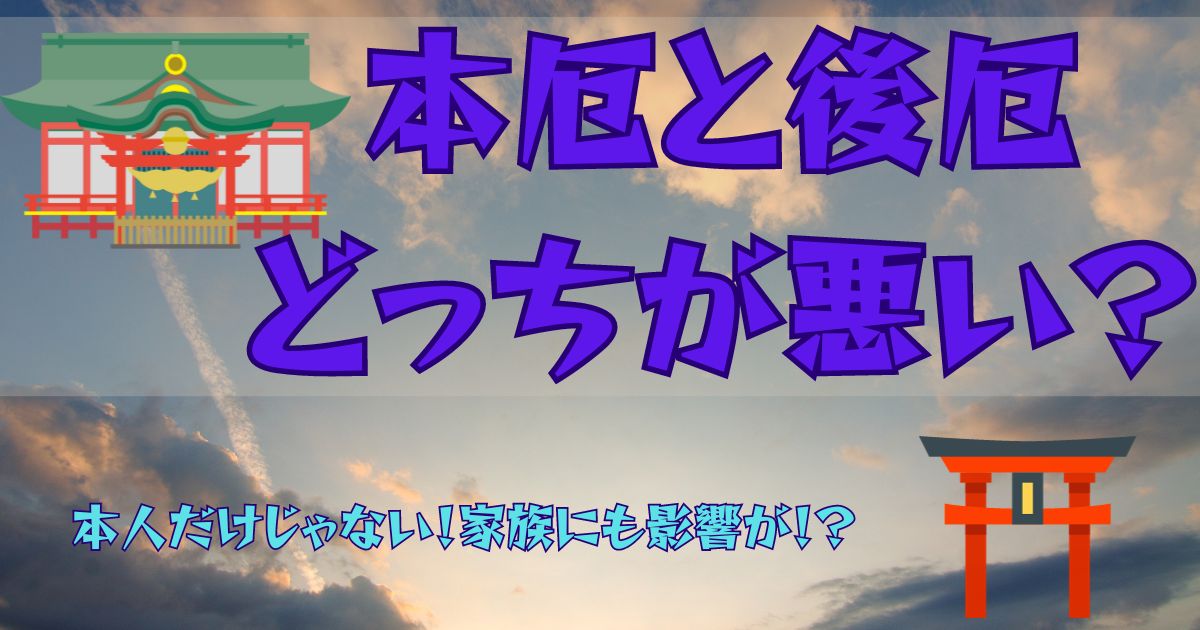
コメント